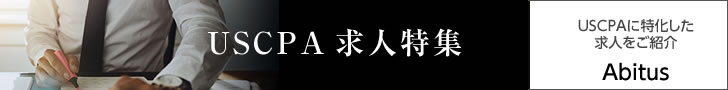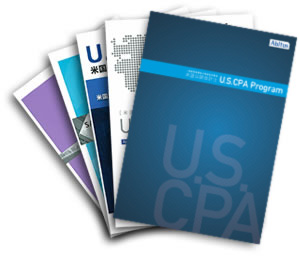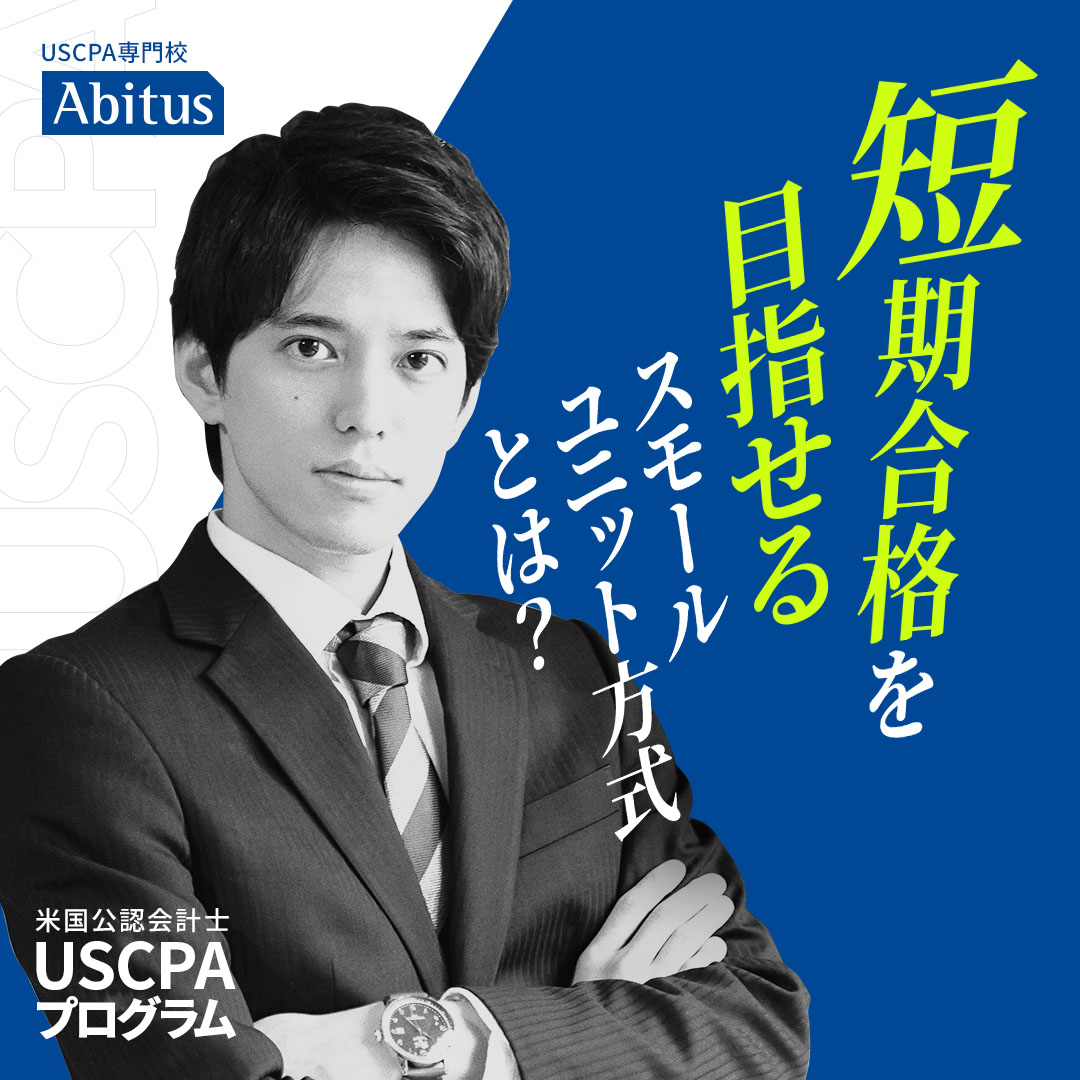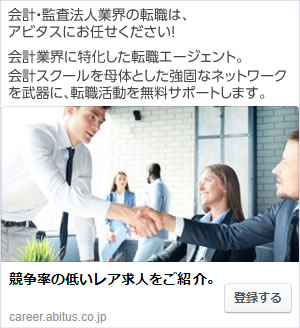第95回 USCPA CMレポート
実施日: 2013年10月20日(日)
【Guest】 BALさん

ゲスト紹介
大学卒業後、大手都市銀行に就職。
国内3か店において主に中小企業を担当し、8年間勤務。 その後、現在就業中の事業法人に転職し8年目。CFO4年目。 現在は、財務経理の他に生産拠点の責任者として購買、工程管理、SCMなども担う。
USCPAを取得しようと思ったのは、現職に就いてからで、銀行にいて財務はわかっていたが、会計の仕訳を切れるかというと切れなくて、会計を勉強しようと思い、簿記から始めて2級まで取得。
その後、2007年12月よりUSCPAの学習を開始、2010年に合格を果たした。 (出願はニューハンプシャー州、合格後、ワシントン州でライセンス取得)
USCPAのBALさんに質問
- ゲスト
- 参加者
- 司会
銀行を辞めた後は、ずっと同じ会社で働かれているんですか?
では今の会社に転職した時は、最初からCFOとしての仕事を探して、最初からCFOとして入社されたのですか?
先ほど話していた仕訳を切るというのは、ただ単に会計システムで伝票を入力するとかそういう意味じゃないですよね?
何故、それが重要なのかがわからないのですが。
我々が決算書を見て、経費のパレート分析をしたり、課題をあぶり出して改善策を立てて、アクションプランを作るなんて言う時に、ベースになるべき資料そのものに信頼性が無ければ、上の方で色々と話しても仕方ないでしょう、と思うんですよね。
そうなると仕訳をきっちりと切るというのが後々大事なのかなというのがひとつ。 それとやはりミスってあるじゃないですか、そうしたミスを一人に背負わすわけにはいかなくて、上司が引き取ってあげないといけないという意味で、ちゃんとチェックしてやらないといけないと思います。
あくまで中小企業のCFOですので、全部できないといけないんです。 どういうCFOを目指すかにもよりますが、いきなりCFOとしてある会社に入るってことは、何らかの問題がその会社にあるってことを覚悟しないといけないんです。再生案件などやりたいと思うなら特に。
大企業のようにスタッフも充実していないかもしれませんし。 小口現金の出納や仕訳の入力など基本的なことをできる人材を育成もできなければなりません。
目的意識を持って経理実務をひと通りやってきた人は、スタッフを監督する立場になっても勘どころが掴めていると思いますし、結構そういう実務を経験すると、USCPAのAUDITで勉強したところがより深く理解できると感じましたね。
USCPAの勉強を始めたのは、今の会社に入ってからということですが、日系なのにUSにしたのは何か理由があったのですか?
以前と、現在、経営者の一員としての働き方、考え方はどう変わりましたか?
中小企業のCFOというのは、どういった業務、どういう責任の範囲で会社をドライブしているのでしょうか?
会社で色々な問題があれば、現場に首を突っ込んでいくという立ち位置で自分の仕事の範囲を決めずにやっていきたいと思ってます。
転職の時に中小企業に企業規模を落とすというのは勇気がいりましたが、でも、おそらく自分一人の力で会社の隅々まですべて把握が出来る規模感ってこれくらいだろうと思ったんです。
同じ財務経理だけでも大きい会社になれば、売掛や固定資産だけ専門でやっている人とかいて、財務経理だけでも全貌を掴めないですよね。ましてや他の部署なんて、何の仕事をしているのか、どんなプロジェクトをやっているか全くわからないじゃないですか。
経営者でいる以上は会社の隅々まで全部自分ひとりで把握できる範囲で、メーカーっていうものはどういう作りになっているのかをわかりたかったんですね。
経理であれば会社のお金の流れが最終的にすべて集まり、トレースしていけば、会社で起こっている事がすべて見えてきますので、そういった意味では口を挟みやすい立場かなと。 そこで起こっている問題ってお金を無駄使いしているとかだけではなくて、品質保証上、こういう対応って本当に良いんでしょうかという話も出てくるわけで、そういう話にも極力自分なりの意見を持つという感じですかね。
それが私の仕事の範囲に関しての考え方です。
責任感とか自分ひとりの判断が間違っていたらとか考えますよね。
つまり「現状通り行く」という事を消極的に選択していると思うんですね。これは止めたい。判断、決断は明示しないといけないと思います。
そのあたりを意識していると自分のところで意思表示しないといけないことが結構あって、この判断が合っているのか間違っているのかなんてわかりません。
ただ、答えを出さずに惰性で進むより、ほどほどの答えでも同じ方向を向く方が強いと思ってます。
経営者だから厳しい決断をしなければいけないという時に、部下の皆さんたちとの関係というのは、どのようにしているのでしょうか?
上の方のジレンマとしては、部下が全然動かないみたいな事を言うんですが、私はもっと上がしっかり方向性を出して、いつまでに誰が何をするのか、明確に落としてあげないとやっぱりなかなか人間って動きづらいと思っているんです。
部下との関係で言えば、判断に至った狙いだとか経緯だとかをしっかり説明していこうとしています。
上場企業のCFOっていうのは株主にAccountabilityを発揮しないといけないというのがあって、それは面倒くさそうですよね(笑) でもAccountabilityを発揮することで株主から資金を集めるように、従業員に対するAccountabilityもあると思うのです。
自分たちのやろうとしている事を株主に理解してもらうのと同様に従業員にも言えないといけないと思うんです。
そこを手を抜いて売上伸ばせ、コストを削減せよと言われても誰もついて来ないと思うんですね。従業員に対してのAccountabilityがひとりひとりのモチベーションになると思っているので、良好な関係を保つようにやっていこうとしています。
自分でも納得が行かない事も伝えていかなければならないと思うのですが、どうやって伝えているんでしょうか?
間違えていますよと。そういう意味では私は結構面倒くさい部下かもしれません。恐らくこの問題は、自分が社会人としてどうありたいかというスタンスそのものと思います。
私はUSCPAライセンスホルダーですが、会計でもない英語でもない何処に自分のプロフェッショナリズムを置くかというと正しい事は正しい、正論をしっかりと貫いていこうというところだと思うんですね。
ただそのまま伝えるといっても、伝書バトでは人はついて来ないですよね。やっぱりいちばん響くのは自分の言葉で話す事ですよね。
将来、上場しようと言う考えはないんですか?
今、都市銀行で働いている立場なのですが、銀行を辞めてしまって損だったなというか、失敗だったなと思うことはありますか?
一時、海外に行きたいなと思っていて、希望を出していたんですけども、なかなか通らなくて。
今は本当にシンガポール、マレーシア含めアジアに結構行っている人がいるので、そこだけは羨ましいなと思いますけどもね。 それ以外に関してはあまり無いんですよね。事業法人のCFOの方が得難い経験をしてると思いますので。
銀行にいた時はUSCPAを学習しようと思っていたわけじゃないんですよね?
銀行を辞めてから事業法人のマネジメントをやるといろいろ勉強しないといけないことがたくさん見えてきて、本を読む機会が増えました。USCPAも体系的に会計を理解する必要に応じて始めたとも言えます。
原価計算もそうで、これを幾らで仕入れて、幾らで作って、幾らで売って、利益は幾らですかというのがわからなくて、、、プランを立てようにもその為のベースが何もなくて、そもそも原価の概念から変えていこうと思うと財務経理だけでは完結しないし、社内全体を巻き込まないとならないし、そうするとプロジェクトを立ててやりましょうかという時に自分が前職でプロジェクトを立ち上げたこともなかったし。
最後は、本を読むか人に聞くかして勉強しながら、さらに自分なりのオリジナリティーを出しながら、手探りでやってきたという感じです。